懐徳堂
 「懐徳」の由来には、創設時の関係者の書き残したものがないため、推測の域を出ないが、幾つかの説がある。『懐徳堂考』を著した西村天囚てんしゅうは、『論語』里仁篇の「君子懐徳、小人懐土(君子は徳を懐い、小人は土を懐う)」をあげ、また、その著『懐徳堂考』において、『詩経』大雅皇矣篇の「予懐明徳(予明徳を懐う)」をあげている。戦後、大阪大学文学部教授となった蔵内数太は、『書経』周書洛誥にある「王〓殷乃承叙、万年其永観朕子懐徳(王殷をして乃ち承叙せしめば、万年それ永く朕が子を観て徳を懐わん)」を出典ではないかとした(「懐徳ということ」『懐徳』54号5頁、懐徳堂記念会、1985年)。脇田修も、蔵内説を支持している(『懐徳堂とその人びと』18頁、大阪大学出版会、1997年)。
「懐徳」の由来には、創設時の関係者の書き残したものがないため、推測の域を出ないが、幾つかの説がある。『懐徳堂考』を著した西村天囚てんしゅうは、『論語』里仁篇の「君子懐徳、小人懐土(君子は徳を懐い、小人は土を懐う)」をあげ、また、その著『懐徳堂考』において、『詩経』大雅皇矣篇の「予懐明徳(予明徳を懐う)」をあげている。戦後、大阪大学文学部教授となった蔵内数太は、『書経』周書洛誥にある「王〓殷乃承叙、万年其永観朕子懐徳(王殷をして乃ち承叙せしめば、万年それ永く朕が子を観て徳を懐わん)」を出典ではないかとした(「懐徳ということ」『懐徳』54号5頁、懐徳堂記念会、1985年)。脇田修も、蔵内説を支持している(『懐徳堂とその人びと』18頁、大阪大学出版会、1997年)。
なお、『論語』里仁篇の「子曰、君子懐徳、小人懐土、君子懐刑、小人懐惠」の解釈については、古注・新注とも、君子と小人の在り方を対比したものと理解する(その場合の刑は法則という良い意味)が、荻生徂徠『論語徴』は「君子徳を懐えば小人土を壊い(土地に安住する)、君子刑を壊えば小人恵を壊う」との別解を提示している。その場合、この里仁篇の孔子の言葉は、『論語』為政篇の「道之以政、齊之以刑、民免而無恥。道之以徳、齊之以禮、有恥且格(格は古注によれば正、新注によれば至る)」という徳治主義の主張に類似することとなる。
甃庵・冽庵
懐徳堂の二代目学主中井甃庵(名は誠之、通称は忠蔵、竹山・履軒の父)は、『非物篇』の著者として知られる五井蘭洲らんしゅう(名は純禎、通称は藤九郎、懐徳堂助教)とともに懐徳堂の基礎を築いた。二人は、五井、中井の姓の「井」に因んで、各々の号を付けた。中井甃庵は『周易』「井」卦六四の「井甃无咎」より「甃」を取って「甃庵」を号とした。「井甃す。咎无し」とは、井戸の内壁もすでに修繕され、あとは人に用いられるのを待つばかりであるから、咎はない、の意。一方、五井蘭洲は、九五の「井冽寒泉食」から「冽」を取って「冽庵」を別号とした。「井冽くして、寒泉食わる」とは、井戸の水が清冽に澄み、湧き出る冷たい泉水が人に飲食される、の意である。その象伝の解説によれば、寒泉が食われるのはその徳が中正だからであるという。
尚志
 中井竹山の筆になる「尚志」と記された書幅がある。その出典は、『孟子』尽心篇上に見える孟子の言葉。斉の国の王子〓が士たる者のつとめるべきことを質問したのに対して、孟子は、志を尚くすることだと答えた。〓がその具体的な意味を問うと、孟子は、仁義に志すことと答え、さらに、一人でも罪のない者を殺せば仁とはいえず、自分の所有物でもないのに奪い取るのは義ではなく、常に仁に身を置き、義を踏み行えば、大人(りっぱな人間)になれる、と説いた。「王子〓問曰、士何事。孟子曰、尚志、曰何謂尚志、曰仁義而巳矣、殺一無罪非仁也、非其有而取之非義也、居惡在仁是也、路惡在義是也、居仁由義、大人之事備矣(王子〓問いて曰く、士何をか事とする。孟子曰く、志を尚くす。曰く、何をか志を尚くすと謂う。曰く仁義のみ。一無罪を殺すは仁に非ざるなり。其の有つに非ずして之を取るは義に非ざるなり。居悪くにか在る、仁是れなり。路悪くにか在る、義是れなり。仁に居り義に由れば、大人の事備わる)」。
中井竹山の筆になる「尚志」と記された書幅がある。その出典は、『孟子』尽心篇上に見える孟子の言葉。斉の国の王子〓が士たる者のつとめるべきことを質問したのに対して、孟子は、志を尚くすることだと答えた。〓がその具体的な意味を問うと、孟子は、仁義に志すことと答え、さらに、一人でも罪のない者を殺せば仁とはいえず、自分の所有物でもないのに奪い取るのは義ではなく、常に仁に身を置き、義を踏み行えば、大人(りっぱな人間)になれる、と説いた。「王子〓問曰、士何事。孟子曰、尚志、曰何謂尚志、曰仁義而巳矣、殺一無罪非仁也、非其有而取之非義也、居惡在仁是也、路惡在義是也、居仁由義、大人之事備矣(王子〓問いて曰く、士何をか事とする。孟子曰く、志を尚くす。曰く、何をか志を尚くすと謂う。曰く仁義のみ。一無罪を殺すは仁に非ざるなり。其の有つに非ずして之を取るは義に非ざるなり。居悪くにか在る、仁是れなり。路悪くにか在る、義是れなり。仁に居り義に由れば、大人の事備わる)」。
履軒
 中井履軒は享保17(1832)年、兄竹山の2歳下の弟として懐徳堂内で生まれた。名は積徳、字は処叔、通称は徳二。「履軒」あるいは「幽人」と号した。「履軒」という号は『周易』の語に因む。『周易』「履」卦の九二の爻辞に、「履道坦坦、幽人貞吉(道を履むこと坦坦たり。幽人貞にして吉)」とあり、その象伝に「幽人貞吉、中不自亂也(幽人貞吉とは、中自から乱れざるなり)」と説く。正しい道を坦々と履んで野に隠れている人であれば、その心中が穏やかで欲によって乱されることがないから、正しくて吉であるという意味。次項の「水哉」にも通ずる履軒の人生観を反映した号である。
中井履軒は享保17(1832)年、兄竹山の2歳下の弟として懐徳堂内で生まれた。名は積徳、字は処叔、通称は徳二。「履軒」あるいは「幽人」と号した。「履軒」という号は『周易』の語に因む。『周易』「履」卦の九二の爻辞に、「履道坦坦、幽人貞吉(道を履むこと坦坦たり。幽人貞にして吉)」とあり、その象伝に「幽人貞吉、中不自亂也(幽人貞吉とは、中自から乱れざるなり)」と説く。正しい道を坦々と履んで野に隠れている人であれば、その心中が穏やかで欲によって乱されることがないから、正しくて吉であるという意味。次項の「水哉」にも通ずる履軒の人生観を反映した号である。
水哉館
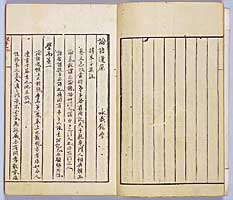 中井履軒は、懐徳堂学派の中で独自の位置を占める。兄・竹山が懐徳堂学主として活躍するのに対し、履軒は三十代半ばに懐徳堂から独立して私塾水哉館を営み、厖大かつ精緻な古典研究を行なった。「水哉館」の名称は、孔子がしばしば水を称えていたということに因む。『孟子』離婁篇下に、孟子の弟子の徐子と孟子との問答が次のように見える。「徐子曰、仲尼亟称於水、曰水哉水哉。何取於水也。孟子曰、原泉混混不舎昼夜、盈科而後進、放乎四海、有本者如是、是之取爾(徐子曰く、仲尼亟水を称して曰く、水なる哉水なる哉と。何をか水に取れる。孟子曰く、原泉は混混として昼夜を舎かず。科を盈たして後に進み、四海に放る。本有る者は是くの如し。是れ之を取るのみ)」。孟子の説明によれば、「水哉」とは、たゆみのない持続的な学問研究の姿勢を、常に流れて止まない水に喩えたものと言える。
中井履軒は、懐徳堂学派の中で独自の位置を占める。兄・竹山が懐徳堂学主として活躍するのに対し、履軒は三十代半ばに懐徳堂から独立して私塾水哉館を営み、厖大かつ精緻な古典研究を行なった。「水哉館」の名称は、孔子がしばしば水を称えていたということに因む。『孟子』離婁篇下に、孟子の弟子の徐子と孟子との問答が次のように見える。「徐子曰、仲尼亟称於水、曰水哉水哉。何取於水也。孟子曰、原泉混混不舎昼夜、盈科而後進、放乎四海、有本者如是、是之取爾(徐子曰く、仲尼亟水を称して曰く、水なる哉水なる哉と。何をか水に取れる。孟子曰く、原泉は混混として昼夜を舎かず。科を盈たして後に進み、四海に放る。本有る者は是くの如し。是れ之を取るのみ)」。孟子の説明によれば、「水哉」とは、たゆみのない持続的な学問研究の姿勢を、常に流れて止まない水に喩えたものと言える。
華胥国
安永8(1776)年6月、中井履軒は48才で中村有則の妹と再婚した。翌年、南本町一丁目に転居した履軒は、その住居に華胥国門の扁額を掲げ、自らを華胥国王に擬した。「華胥国」とは、中国の伝説的な皇帝であった黄帝が夢の中で遊んだという理想国で、そこでは身分の上下がなく、民には愛憎の心がなく、利害の対立もなく、自然のままであったという。その故事は『列子』黄帝篇に次のように記されている。
晝寢而夢、遊於華胥氏之國。……其國無師長、自然而已。其民無嗜慾、自然而已。不知樂生、不知惡死、故無夭殤。不知親己、不知疏物、故無愛憎。不知背逆、不知向順、故無利害((黄帝)昼寝て夢み、華胥氏の国に遊ぶ。……其の国師長無く、自然なるのみ。其の民嗜欲無く、自然なるのみ。生を楽しむを知らず、死を悪むを知らず、故に夭殤無し。己を親しむを知らず、物を疏んずるを知らず、故に愛憎無し。背逆を知らず、向順を知らず、故に利害無し)。
黄帝は、この夢から覚めた後、大いに悟るところがあり、その後、二十八年間、天下は大いに治まって、ほとんど華胥国の如くであったという。また、黄帝が崩御した際、民は黄帝の治を慕って泣き叫び、その悲しみは二百年間続いたという。
この語も、「履軒」や「水哉」に相通ずる性格を持つ語である。なお、その後、履軒は相次いで「華胥国」を冠した書を執筆する。経世については、「華胥国物語」、天文学では「華胥国暦」、歌文では「華胥国囈語」「華胥国歌合」などである。
天楽楼・偸語欄
 中井履軒は、安永8年(1776)に再婚した後、華胥国門の扁額を取りつけた借家の二階の一室を、「天楽楼」と名づけた。これは、『荘子』天道篇の「與人和者、謂之人樂。與天和者、謂之天樂(人と和する者は、之を人楽と謂い、天と和する者は、之を天楽と謂う)」に因んだものである。『荘子』は、人間同士が和することを「人楽」と言うのに対して、人が天の自然と和する境地を「天楽」と評した。そして、この天の楽しさをわきまえた者は、生きているときには自然のままに振る舞い、死んでいくときには万物の変化に従い、静かにしているときには陰の気と徳を同じくし、動いているときには陽の気と波を同じくする、と説いた。この思想は「無心の静けさ」につながっていくが、決して隠者(世捨て人)の立場を説いたものではなく、「天樂者、聖人之心、以畜天下也(天楽とは、聖人の心、以て天下を畜うなり)」とあるように、天下を経営するという理想を表している。
中井履軒は、安永8年(1776)に再婚した後、華胥国門の扁額を取りつけた借家の二階の一室を、「天楽楼」と名づけた。これは、『荘子』天道篇の「與人和者、謂之人樂。與天和者、謂之天樂(人と和する者は、之を人楽と謂い、天と和する者は、之を天楽と謂う)」に因んだものである。『荘子』は、人間同士が和することを「人楽」と言うのに対して、人が天の自然と和する境地を「天楽」と評した。そして、この天の楽しさをわきまえた者は、生きているときには自然のままに振る舞い、死んでいくときには万物の変化に従い、静かにしているときには陰の気と徳を同じくし、動いているときには陽の気と波を同じくする、と説いた。この思想は「無心の静けさ」につながっていくが、決して隠者(世捨て人)の立場を説いたものではなく、「天樂者、聖人之心、以畜天下也(天楽とは、聖人の心、以て天下を畜うなり)」とあるように、天下を経営するという理想を表している。
また、この「天楽楼」の楼上の欄干を、履軒は「偸語欄」と呼んだ。これは、『春秋左氏伝』の語に因む。襄公三十一年の条に、叔孫豹が趙孟の死を予言した言葉として「趙孟將死矣。其語偸、不似民主。且年未盈五十、而諄諄焉如八九十者、弗能久矣(趙孟将に死せんとす。其の語偸くして、民の主たるに似ず。且つ年未だ五十に盈たざるに、而も諄諄焉として八九十の者の如し。久しき能わず)」とある。叔孫豹は趙孟の言葉がなおざりで、とても民の長のようには見えない。また、歳が五十にも満たないのに、くどくどしく、まるで八、九十歳の年寄りのようだから、長くは生きられないだろうと言ったのである。履軒は、これを自らの戒めとして心に刻み、欄干を「偸語欄」と称したのである。
鶉居
うずらのように、居所が一定しないこと。かつて上田秋成と中井履軒とが合賛した鶉図一幅があったという。その図に履軒は「悲哉秋一幅、如聞薄暮聲、誰其鶉居者、独知鶉之情」という画賛を記した。これは、『荘子』天地篇に「夫の聖人は鶉居して〓食(ひな鳥が親鳥から与えられたままに口移しで餌を食べること)し、鳥行して(鳥のように自由に飛び回って)彰わるる無し(夫聖人鶉居而〓食、鳥行而無彰)」とあるように、鶉が棲むところを転々として一定の場所に止まらないことをいう。懐徳堂の外に身を置いて転居を繰り返した履軒の生涯を、そのまま示したような語である。
力學以修己立言以治人
 対句を二つに分けて書き、それを家の入り口、門、壁などに左右相対して掛けたものを「聯」あるいは「対聯」と言った。懐徳堂学舎には、教育的効果を狙って至るところに「聯」がかけられていたという。懐徳堂の外門を入ると、講堂に通ずる庭「已有園」があった。これは、その庭の組格子の中門の左右に掛けられていた竹聯で、中井竹山の筆である。この門の上に竹山の筆で「入徳之門」と記した額がかけられていたことから、この聯は「入徳門聯」と呼ばれる。
対句を二つに分けて書き、それを家の入り口、門、壁などに左右相対して掛けたものを「聯」あるいは「対聯」と言った。懐徳堂学舎には、教育的効果を狙って至るところに「聯」がかけられていたという。懐徳堂の外門を入ると、講堂に通ずる庭「已有園」があった。これは、その庭の組格子の中門の左右に掛けられていた竹聯で、中井竹山の筆である。この門の上に竹山の筆で「入徳之門」と記した額がかけられていたことから、この聯は「入徳門聯」と呼ばれる。
「学を力めて以て己を修め、言を立てて以て人を治む」と読む。全体が特定の古典に直接基づくものではないが、「力学」は努力して学ぶことで、例えば、『太平経』力行博学訣第八十二に「故に聖人は思いに力め、君子は学を力め、昼夜息まざるなり(故聖人力思、君子力學、晝夜不息也)」、『朱子語類』巻第一百二十二呂伯恭に「学に力めて倦まず(力學不倦)」などと見える。「修己」は自己を修養することで、『論語』憲問篇の孔子の言に「己を修めて以て敬す(修己以敬)」などと見える。「立言」は他者に伝えるべき立派な言説・学説を樹立することで、『春秋左氏伝』襄公二十四年に「太上は徳を立つる有り、其の次は功を立つる有り、其の次は言を立つる有り、久しと雖も廃せず(太上有立徳、其次有立功、其次有立言、雖久不廢)」などと見える。「治人」は人を統治することで、『孟子』滕文公上篇に「心を労する者は人を治め、力を労する者は人に治めらる(勞心者治人、勞力者治於人)」などと見える。
この対聯は、こうした古語を組み合わせたもので、自己の修養努力と、それを基にした社会的活動(経世)の重要性を説く内容となっている。中井竹山の『竹山国字牘』も、この聯について解説し、自ら修養努力して、それでも時に逢わなければ、その業は「修身斉家(自身を修めて一家をととのえる)」に止まって「治国平天下(一国を治めさらに天下を平定する)」には至らないが、書物を著して言を立て、進むべき道を明らかして世を正すという功績は、実際に為政者となって政教を行うにも匹敵するものがある、と述べるように、世を正すという気概をこの語に込めていることが分かる。
◆戰々兢々如臨深淵如履薄氷
◆謝朝華於己披啓夕秀於未振
『竹山国字牘』によれば、これは、講堂の北〓(北側の窓)の左右に相対してかけてあったもので「北〓聯」と呼ばれる。竹山は、この両者は対偶(句の構成要素がきちんと対応した、いわゆる対句)ではないが、いずれも名句として、聯に記したと述べている。確かに、前句は、四字ずつの三句からなり、後句は六字ずつの二句からなっていて、構成は全く対応しない。
前句の十二字は、『詩経』の語。『詩経』小雅・小旻の詩に「戦々兢々として、深淵に臨むが如く、薄氷を履むが如し(戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰)」と見える。また、『論語』泰伯篇には、孔子の弟子の曾子が臨終に際してこの語を引いたとされる。曾子の言は、「曾子疾あり。門弟子を召びて曰く、予が足を啓け、予が手を啓け。詩に云う、戦々兢々として、深淵に臨むが如く、薄氷を履むが如しと。而今よりして後、吾れ免るることを知るかな、小子(曾子有疾。召門弟子曰、啓予足、啓予手。詩云、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰。而今而後、吾知免夫小子)」とあるように、孔子の弟子の中でも最も「孝」を重視した曾子が、親から授かった肉体を保全することに細心の注意を払ってきた(身体を傷つけないことは「孝」の第一歩とされた)、その心境を、まるで底なしの淵に臨むような、薄い氷の張った水の上を歩くような「戰戰兢兢」として気持ちであると述べ、また、死によってそうした緊張から解放されることを述べたものである。
後句十二字は、陸機(字は士衡)の語。『文選』所収の陸機の文章論「文賦」に、「百世の闕文を収め、千載の遺韻を采り、朝華を已に披くに謝り、夕秀を未だ振わざるに啓く(收百世之闕文、采千載之遺韻。謝朝華於已披、啓夕秀於未振)」と見える。これは、陸機があるべき文章について、百世の間見られなかった文を収め、千年の間使われなかった韻を用い、すでに開いてしまった朝の華(使い古された表現)を捨て去り、まだ開いていない夕方の華を咲かせようとする、と述べたものである。
このように左右の二句は、構成上も意味上も、直接には対応しないが、前句が生活態度について、また、後句が文章について、いずれも極めて高い理想を掲げていることが分かる。
